育休中にもらえる一時金や手当について、把握していますか?
きっと市役所から案内があるだろうし、その通り対応すれば少なくとも損はしないと思っていませんか?
筆者の場合、認識が甘かったです。少なくとも自分のことは自分で確認し、把握すべきでした。
この記事では、筆者が育児休業を取得するにあたって無知だったために、実際に損をしたことを紹介させていただきます。
結論
筆者は長女が産まれた4年前に1カ月の休暇を取得したのですが、下記3点を知らなかったために、金額にして数十万円ほど損をしました。
- 社会保険料の免除
- 有給休暇を活用する
- 医療費控除を受ける
昨年、長男が産まれる際には、この反省点をしっかり活かすことができました。
社会保険料の免除
育児休業時に受ける最大のメリットが、社会保険料が免除される点です。これが本当に大きいです。
ただ、育休中に賞与が支払われる場合については、注意が必要です。
賞与にかかる社会保険料が免除となるには
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となりました。
例えば6月25日に賞与が支払われる場合、6月末日を含んで連続して1カ月の育児休業をとる必要があります。
- 育休期間が2週間のみの場合は、賞与にかかる社会保険料は免除されません。
- 月末を含めて1カ月休む場合でも、有給休暇を組み合わせる場合は注意が必要です。
筆者の失敗談
前述の通り、4年前に長女が産まれたときは1カ月ほど休暇をとりました。内訳としては、有給休暇2週間+育児休業2週間でした。
そしてたまたまですが、上記の休暇期間中に賞与の支払いがありました。
長女が産まれた年は会社の業績がよかったので、例年に比べて賞与も高かったのですが、賞与支払月の月末を有給休暇としていたので、結果として社会保険料の免除を受けることができませんでした。

社会保険料の免除という制度をそもそも知らなかったので、できる限り有給休暇を使いたいと思っていました。賞与がよかっただけに、社会保険料の支払いは痛かったです…
有給休暇を活用する
ほとんどの会社で、育休中は給与が支払われないと思います。筆者が勤める会社も、給与の支払はありませんでした。
ただ、全くの無給だと生活できないですよね?そこで、「育児休業給付金」があります。



育休中の給与の支払いについては、就業規則に書いてあると思います。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、1歳未満の子どもを育てるために育休を取得する雇用保険の被保険者が対象です。以下のすべての条件を満たす場合に、母親・父親問わず給付金が支給されます。
支給条件
- 育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 育休中に支払われる賃金が、休業前の賃金の80%未満であること
- 育休中の就業が、1ヶ月あたり10日以下、または80時間以下であること
1カ月当たりの支給額
180日まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
なお、支給額には上限と加減があります。
育児休業給付金の支給要件の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
有給休暇との相違点
有給休暇と育児休業、筆者のような無知の一般社員からすると同じ休みなんですが、実は扱いが全く異なります。例えば筆者が勤める会社の場合、育児休業は無給ですが、有給休暇の取得は労働日として扱われ、通常の給与が支払われます。
育児休業給付金は社会保険料だけではなく所得税や住民税も非課税になるみたいだし、手取りベースだったらほとんど変わらないんじゃない?
と思ったそこのあなた。4年前の私です。
2025年4月からは出生後休業支援給付金という制度も始まったので、期間によっては手取りベースだとほぼ変わらないと思います。
ただ、注目していただきたいのが賞与です。筆者が勤めている会社の場合、就業規則において賞与の算定方法が決まっており、実際に勤務した日数を考慮する計算式になっています。



仮に2カ月育休をとると、賞与計算において本来もらえる賞与(年額)の10/12に減額されてしまうんです。一方で、2カ月有給休暇を取得した場合は1年分の賞与をもらえます。
結局どちらをとるべき?
有給休暇が余っている場合、有給休暇と育児休業のどちらをとるべきか、悩みますよね。下記では、賞与が年1回で120万円、社会保険料が15%(18万円)で、2カ月休む場合を前提として、検証しました。
- 2か月間:有給休暇の場合
-
賞与120万円-社会保険料18万円=手取り102万円
- 2か月間:育児休業の場合
-
賞与100万円(120万円×10カ月/12カ月)-社会保険料0円=手取り100万円
- 1カ月間:有休+1カ月間:育休の場合
※賞与に関して社会保険料の支払い免除となる期間で育休取得 -
ボーナス110万円(120万円×11カ月/12カ月)-社会保険料0円=手取り110万円
上記前提だと、有休と育休を組み合わせる形が一番メリットがありそうですね。
ただ、社会保険料の免除は育休期間中ですが、育休を取得したことによる賞与の影響は翌年分で表れるはずなので、翌年の賞与の金額によって結果は変わると思います。



前提条件によっても結果は変わると思います。正確な計算については専門家や所属する会社の担当者にご確認ください。
医療費控除を受ける
妊娠中の健診費用や出産費用は医療費控除を受けることができるって知ってますか?恥ずかしながら、筆者は全然知りませんでした。
高校(男子校)の同窓会で飲んでいた時に、「医療費控除のために初めて確定申告をした」という話を聞き、「なにそれ?」となりました。
医療費控除とは
申告者(およびその家族)が1年間に支払った医療費が一定の基準額を超えるとき、確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
詳しくは、最寄りの税務署もしくは国税庁のホームページをご覧ください。
確定申告について
筆者はサラリーマンなので会社の年末調整しか経験がなく、なんとなく確定申告はハードルが高いと思っていました。
ただ実際に申告してみたところ、マイナンバーカードをつかってマイナポータルから比較的簡単に申告できました。特に出産費用の医療費控除は対象者も多いためか、いろいろなサイトで丁寧に説明してくれているので、確認してみてください。
育休期間中に2時間ほど時間を確保して、申請方法など確認してみてもいいと思います。



時給換算するとかなり割がいいと思います。お小遣い稼ぎと思って確認してみることをお勧めします。
筆者の場合
2人目の出産費用に関して確定申告し、10万円ほど還付金を受け取りました。子どもが生まれてお金がかかる時期だったので、とても助かりました。
ちなみに、還付申告(所得税の確定申告によって払いすぎた税金が戻ってくる)の場合は、該当年の翌年の1月1日から5年以内に行えば問題ないそうなんですが、引っ越しなどで当時の明細を紛失しており、諦めました。
まとめ
この記事では、私が育休前に知らずに失敗した下記の3点を中心に説明させていただきました。
もちろん、会社によって賞与の決まり方は違うでしょうし、育休と有休を組み合わせることが難しい人だっていると思います。
ただ、特にパパが育休を取得する場合、取得開始時期や期間についてはある程度融通できるのではないでしょうか?
金銭的なメリットを受けることができる場合もあるので、これから育休取得を考えている方は、一度検討してみる価値があると思います。
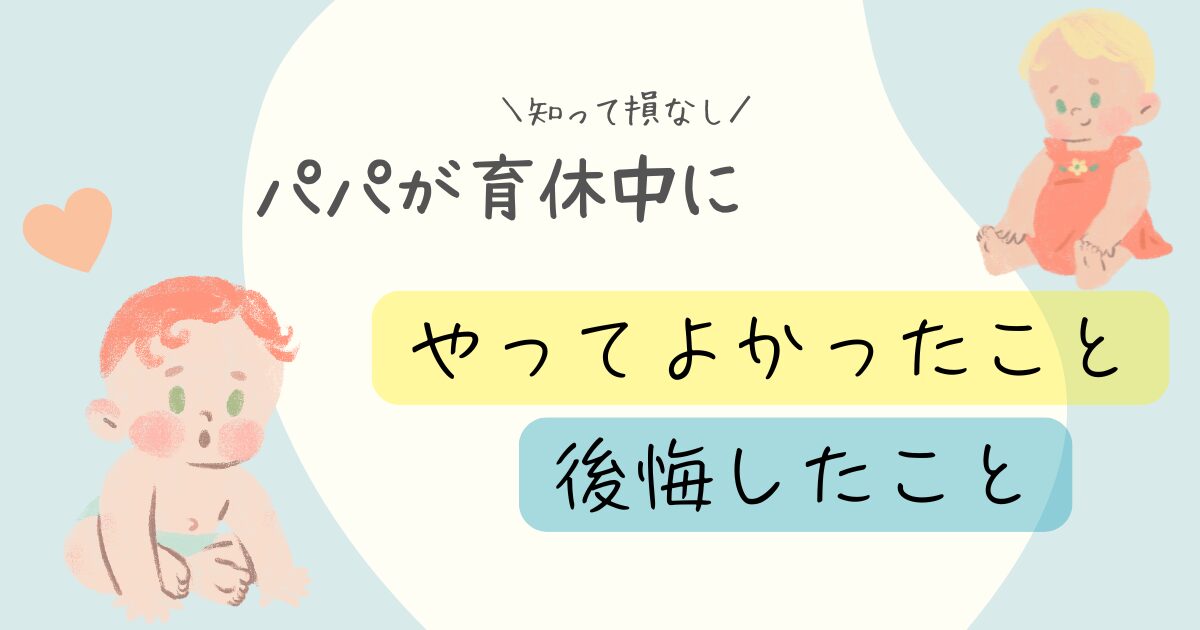
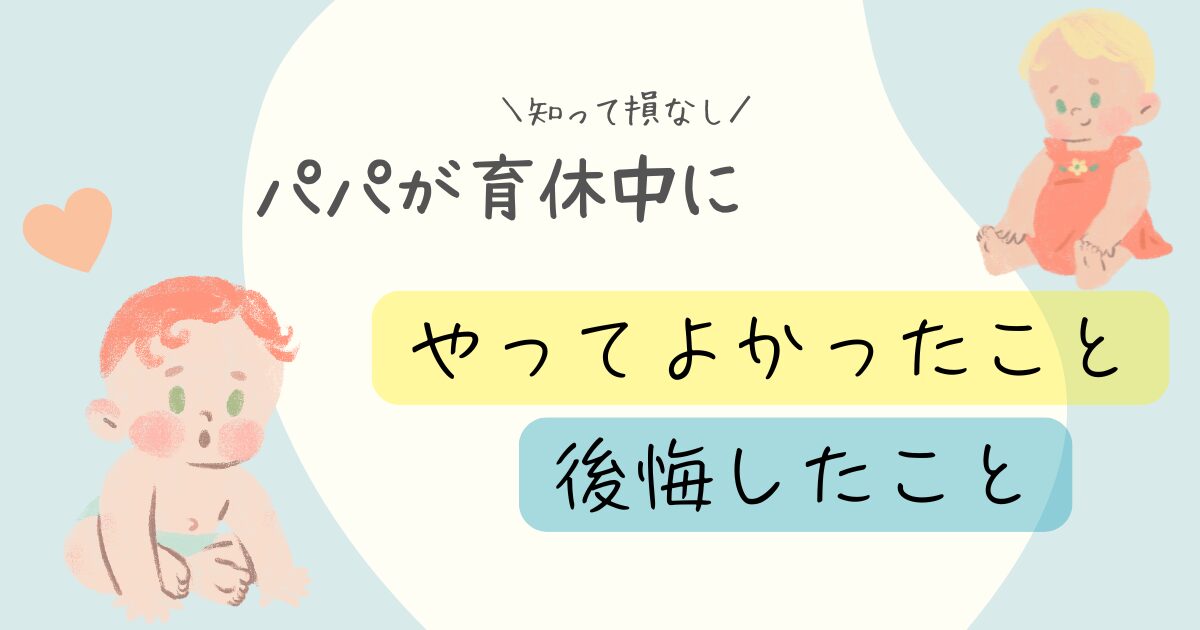
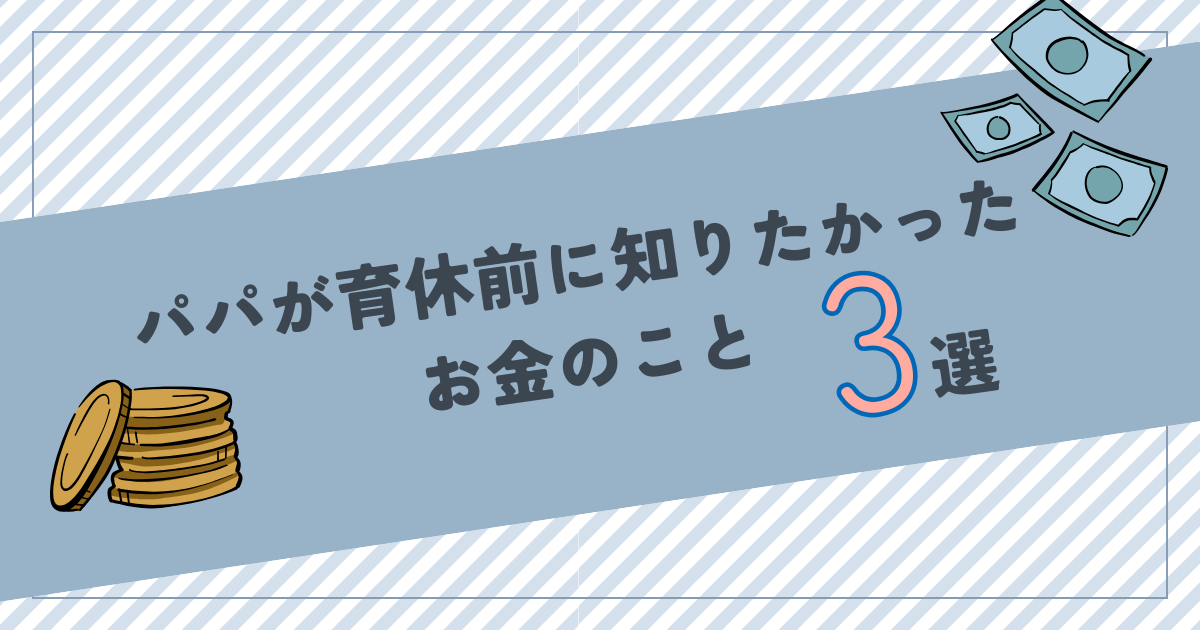
コメント